こんにちは、うえにーです。
今回は、羽田康介さんが書かれた、問題解決力を高める「推論」の技術の書評です。
昨今の日本では年功序列の崩壊、少子高齢化社会、人生100年時代、コロナ禍etc.。不安を駆りたてるような様々なキーワードがメディアで叫ばれています。
そんな現代社会は「VUCA(ブーカ)の時代」とも言われ、不確実性の高い世の中になりつつあります。今まで常識だった「教育→仕事→引退」といった、退職金と年金で老後は悠々自適に暮らすというロールモデルは崩壊したようにも思います。
そんな複雑な社会を生き抜くために必要なのが「推論力」です。その推論力を学べるのが、今回ご紹介する「問題解決力を高める「推論」の技術」です。
推論力とは?

日々の仕事で、こんなことに直面することはないでしょうか。
- 何かを考えないといけないが何を考えていいかわからない
- 浅い分析しかできない
- 伝えたいことが伝わらない
- 仕事が締め切りのギリギリになることが多い
- 自分の提案が通らない
このような悩みを解決できるのが「推論力」です。
推論力とは未来の事柄に対して、筋道を立てて推測し、論理的に妥当な結論を導き出す力
推論のプロセス
①事実を認識する→②問題意識を持つ→③推論する→④仮説を導き出す→⑤仮説を検証する→⑥結論を出す
私が現在働いている会社でも、事実を認識し問題意識をもつ人はたくさんいます。ですが、推論する人が非常に少ないです。
また、社会を出て働いている方だとお分かりだと思いますが、どんな些細な仕事においても「正解」がないものがほとんどです。いかに妥当性の高い事柄を論理的に仮説し、決定権者を説得できるようもっていくかが大切です。
しかし、日本の教育は「正解をいかに早く正確に説くか」については多く訓練されていますが、論理的に思考することは苦手で、「頭がいいのに仕事ができない人」を作ってしまっているように思います。
このような目に見えない推論のスキルは、学歴や資格、職歴などの目に見えるものよりも希少価値が高く、目に見えないことは傍から見て真似されにくいスキルとも言えます。
推論力を身につけるには?

推論力を身につけるには主に3つあります。ひとつずつ紹介していきます。
1.帰納法(きのうほう)
帰納法=複数の事実から共通点を発見して結論を導き出す推論法
まずは帰納法から。また帰納法には2種類あります。
①「観察的帰納法」=観察を通じて得られた複数の事実から「直接的に」共通点を発見する方法
②「洞察的帰納法」=洞察を通じて得られた複数の事実から「洞察を通して」共通点を発見する方法
まずは観察的帰納法から見ていきましょう。
例えば、
事実①:社内のAさんは、静かな性格だ
事実②:社内のBさんは、静かな性格だ
事実③:社内のCさんは、静かな性格だ
共通の発見:うちの会社の社員に共通するのは、静かな性格であることだ
結論:よって、うちの会社は静かな社風だ
これは観察を通じて得られた複数の事実がベースになっている思考法です。
次に洞察的帰納法を見ていきましょう。
例えば、
事実①:水は「飲めるもの」だ
事実②:水は「洗えるもの」だ
事実③:水は「火を消せるもの」だ
共通の発見:この3つの共通点は、モノ(=水)を抽象化して「コト」として捉え直したこと
結論:「モノ」から「コト」を抜き出すと、その実体が持つ複数の「価値」を発見できる
洞察的帰納法は物事を洞察し、目に見えないものを見抜き出します。同時に洞察力も必要となるため、観察的帰納法に比べると少し習得するのに時間を要します。
2.演繹法(えんえきほう)
演繹法=前提となるルールに物事を当てはめて結論を出す推論法
2つ目の思考法は演繹法です。
演繹法の前提となるルールとは、目的や目標、方針、ビジネス上のセオリーなどのことです。社会人であれば、現在働いている会社などで社内規定や経営方針などが必ずあると思います。その前提のルールに従って、推論していく方法が「演繹法」です。社会人にとっては馴染み深い思考法かもしれません。
例えば、「働きがいの向上は、我が社の方針」という前提としてのルールがあれば、
当てはめる物事:社内表彰制度の導入は、働きがいの向上に貢献する
導かれる結論:よって、社内表彰制度を導入すべきだ
というふうになります。
このように前提をもとに理論を当てはめていく方法です。
3.アブダクション
アブダクション=「起こった現象」に対して「法則」を当てはめ、起こった現象をうまく説明できる仮説を導き出す方法論
3つ目の思考法はアブダクションです。
要は起こった問題を解決するために論理的に仮説を立てることです。上司や裁量権のある人を説得できるように問題を定義し、その問題を解決するためのストーリーを組むことです。
例えば、
起こった現象:売上が落ちた
法則の当てはめ:買う人が減れば、売上は落ちる
導かれる仮説:よって、売上が落ちたのは買う人が減ったからに違いない。
というふうになります。
ただ、売上を落としている原因は買う人が減ったというだけではないケースも多々あります。その場合、別途売上が減っている原因を探す必要があります。そんな時に非常に使いやすいのが「ロジックツリー」です。
ロジックツリーに関しては、「【要約】世界一やさしい問題解決の授業をわかりやすく解説」で説明しているので、そちらで見てください。
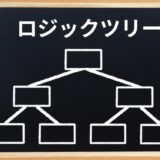 【要約】世界一やさしい問題解決の授業をわかりやすく解説
【要約】世界一やさしい問題解決の授業をわかりやすく解説
まとめ
今働いている会社でも、部下が上司に対して答えを求める社員が多いように思います。自分では何も考えずに答えを上司(他人)に求めて、楽して答えをもらうのではなく、自分の中で推論し考えを構築する必要があるように思います。
正解がない時代だからこそ、自分の頭で思考することが大切です。
仕事の仕方に悩んでいる人や今の仕事をさらにレベルアップしたい人などの参考になれば幸いです。
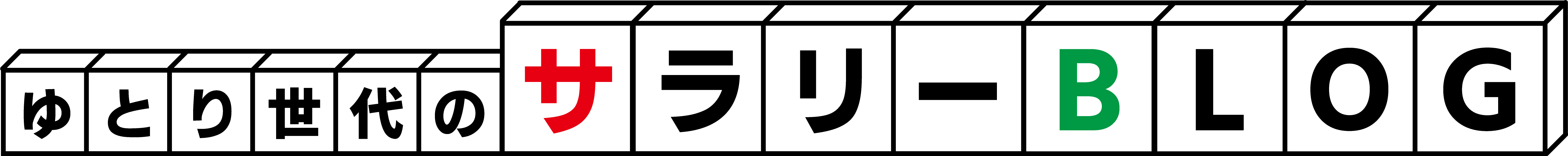



コメントを残す