日々を生活していると毎月会社からお金が支払われ、そのお金を節約して毎月貯金する人もいれば、ほしいものを買う人もいます。近年、人生100年時代を迎えるにあたって、生き方や働き方を見つめ直すきっかけになっています。そのような変化にはお金の基礎知識が必要ではないかと感じます。
しかし、お金については、学校や会社では教えてくれないというところに落とし穴があります。なので、一度お金の基本について自分で一から学ぶ必要があると思います。今回は、ファイナンシャルリテラシー(※)を上げる!お金の基礎知識についてご紹介していきます。
※ファイナンシャルリテラシー(Financial Literacy)とは、お金に関して読み書きできる能力という意味です。つまり「お金の知識」を意味します。
 タコ
タコ
今回はこちらの本を参考にさせてもらいました。項目ごとに分かれており、イラストも多く非常に読みやすい本でした。

節約・貯蓄・投資の前に 今さら聞けないお金の超基本(著:坂本綾子)
Contents
お金の変化
もともとお金は物々交換の不便さを解決するために生まれました。その変化してきたお金の歴史をおさらいしましょう。
最近ではPayPayなんかも出てきて、お金の支払い方だけでもいろんな選択肢があるので今の自分や少し近い将来にあったやり方を考えましょう。
お金の6つの機能
書いていることは当たり前ですが、お金の機能について、復習しましょう。お金を全体的に俯瞰することで気づきもあるので、自分の普段のことも考えながら見るのがおすすめですね。
お金を貯める
お金を貯めるについては、バビロン大富豪の教えでも紹介しましたが、大富豪になるための黄金に愛される七つの道具との一つ目に書かれている「まずはじめに収入の十分の一を貯金すること」です。人間の欲望には際限がないので、まずは給料が入ったら、貯金用の口座に最低でも収入の十分の一を入れるようにしましょう。
 【バビロン大富豪の教え】お金と幸せを生み出す黄金法則を解説
【バビロン大富豪の教え】お金と幸せを生み出す黄金法則を解説
老後に備える
老後に備えるにはまずは年金ですね。年金には大きく分けて2種類あります。
公的年金
国籍を問わず、日本に住む20歳以上60歳未満の人は全員が国民年金保険に入ります。そして65歳に申請すると基礎年金を受け取れます。会社員や公務員は、厚生年金保険にも加入します。その分、年金額は増えます。この2つのことを公的年金と言います。
 タコ
タコ
実はマクロ経済スライド(※)というものがあって、公的年金がなくなるということはないのです。(ただ給付水準は下がる可能性は高いですが。)
※マクロ経済スライドとは、そのときの社会情勢に合わせて年金の給付水準を自動的に調整する仕組みです。
私的年金
私的年金とは、公的年金の上乗せの給付を保障する制度のことです。私的年金には、「企業が自社の退職金制度に関する福利厚生の一環として実施する年金」と「個人が任意で加入する年金」があります。
「企業が自社の退職金制度に関する福利厚生の一環として実施する年金」
- 企業型確定拠出年金
- 厚生年金基金
- 確定給付企業年金
「個人が任意で加入する年金」
- 個人型確定拠出年金(iDeCo<イデコ>)
- 国民年金基金
お金を増やす
1970年〜1980年代は、本業で稼いだお金を定期預金に入れるだけで、郵便貯金の10年定期預金(※)の金利が、実に8〜12%もあったんです。
※定期預金とは、預け入れから一定期間お金を引き出せない預金のことで、一般的には普通預金よりも金利が高く設定されています。
年金額にしても金額が高かったし、寿命も今よりは短かったのであまりお金について考えなくても、何とかやっていけましたが、低金利・年金の給付減額・人生100年時代にはお金を増やすことを視野に入れておいた方がいいでしょう。ではどのようにして増やせばいいのでしょうか?
資格取得する
資格を取得することで仕事の幅が広がる可能性があります。会社によっては業務にかかわる資格の取得を推薦し、資格手当を出すところもあります。
隙間時間でプチ副業
好きや得意を活かして収入を得る方法です。流行のユーチュ―バーやアフィリエイト、WEBデザイナー、ライター、ネットオークション、ハンドメイドの販売、翻訳、家庭教師など様々あります。
投資
投資商品はたくさんあるので、どれを選ぶか迷ってしまいますが、まずはどんなものがあるかを知っておきましょう。
- 債権
- 投資信託
- 株式
- 外貨預金
- REIT(不動産投資信託)
- 不動産
- 確定拠出型年金
- NISA
- つみたてNISA
- 金
- FX
上記は一例ですが、自分にあったものはなんのかを模索していきましょう。
ファイナンシャルリテラシーを上げる!お金の基礎知識まとめ
せっかくお金についての本を読んだり、ネットで検索したりなどして理解でき、ファイナンシャルリテラシーが上がったとしても、自分の行動をおこすところまでしないとただの評論家になってします。これを読んだ方は、ぜひ今日から行動に移して実践していきましょう。
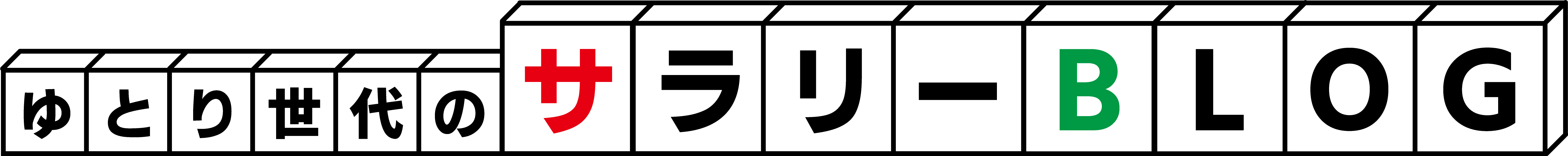



コメントを残す